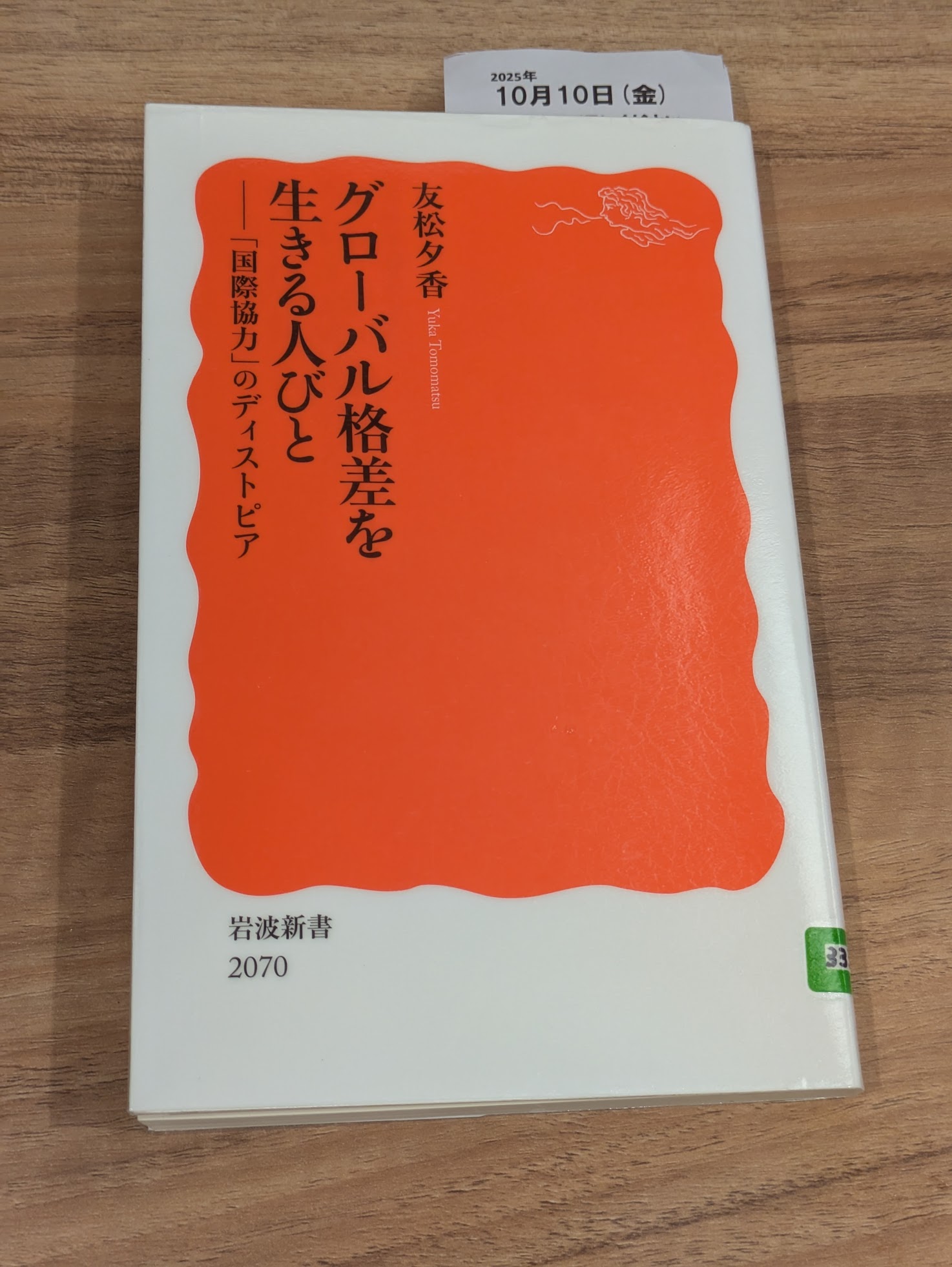ブルキナファソなどいわゆる新興国と分類される国々の人が欧州あるいはフランス等の旧宗主国に対する不信に得心がいったというのが第一の感想である。欧州諸国の多くが人権をとても大事にしているのも事実だが、スネに傷もある。植民地時代の歴史であり、本書では通貨システムの問題が指摘されているが、今も解消されていない見えにくい支配関係が残っている。為政者は国益を維持・拡大すると言わなければ民主主義社会では権力を維持することはできないが、それは搾取の温存を指向することにほかならない。
著者はUCB出のJICAブルキナファソで経験を積んだ人だ。本書を読んでいるとその誠実さが伝わってくる。
ロマンス詐欺の話は結構衝撃的だ。明らかに搾取されていることに気がついているから、詐欺が犯罪であると考えていても、巨悪に比べれば無視できるものだと考えてしまう。白人からむしっている人がヒーローになっているシーンは私には恐ろしく、また悲しい。改めて、自分が見えている世界は、極めて狭いと感じさせられる。北方領土に住むロシアの人はどう世界を見ているのか気になる。
グローバル格差の解消には大規模な戦争でもなければ数世代ではとても解消できないだろう。国内格差さえ解消には2世代は必要だろう。しかも、今は総じて縮退期だから逆風だ。不当な既得権益でも失うことが耐えられない。扇動者も跋扈し、グローバル格差をさらに拡大して自分の生活を守ろうとする人もいる。その向こうには戦争がある。今起きている悲惨なウクライナ戦争やパレスチナ虐殺は、おそらく比較すれば軽いものだろう。内戦も起きるだろうし、安全・安心は失われていく。移動の自由も失われていくだろう。移動の自由が失われれば、なぜロマンス詐欺が許容されているかを気がつくこともできなくなるだろう。
本書籍を読む人が増えれば、直接行かなくても多少は想像できる人は増えるだろう。
何となく、欧州はきちんとしているというイメージがあるが、理想を追求していても簡単には近づけない。それでも、努力することは無駄ではない。自分たちが良ければそれで良いと思ってしまうようになると、築いたものも崩れていってしまう。加害者としての歴史に向かい合って、やれることをやっていかないといけない。
自分たちは被害者だから、復讐しても良いのだと考えるとその人の中の人間性が壊れていく。恐ろしいことだ。様々な(誰かにとって不都合な)事実が明らかになるのがいけないとは思わないが、長期視点への見識がバランスしている必要を感じる。
ちなみに、ブルキナファソは最近しばしばDrupalの世界で耳にする。DrupalCamp 2025(DrupalCamp Burkina Faso 2025, taking place April 25–26 in Ouagadougou)も開催されているし、2026年も計画されてる。
また、International Federationでも話題に上る(Working memberにも含まれている)。しかし、私は特に意識していなかった。これを機会にブルキナファソのことを知ってみようと思う。