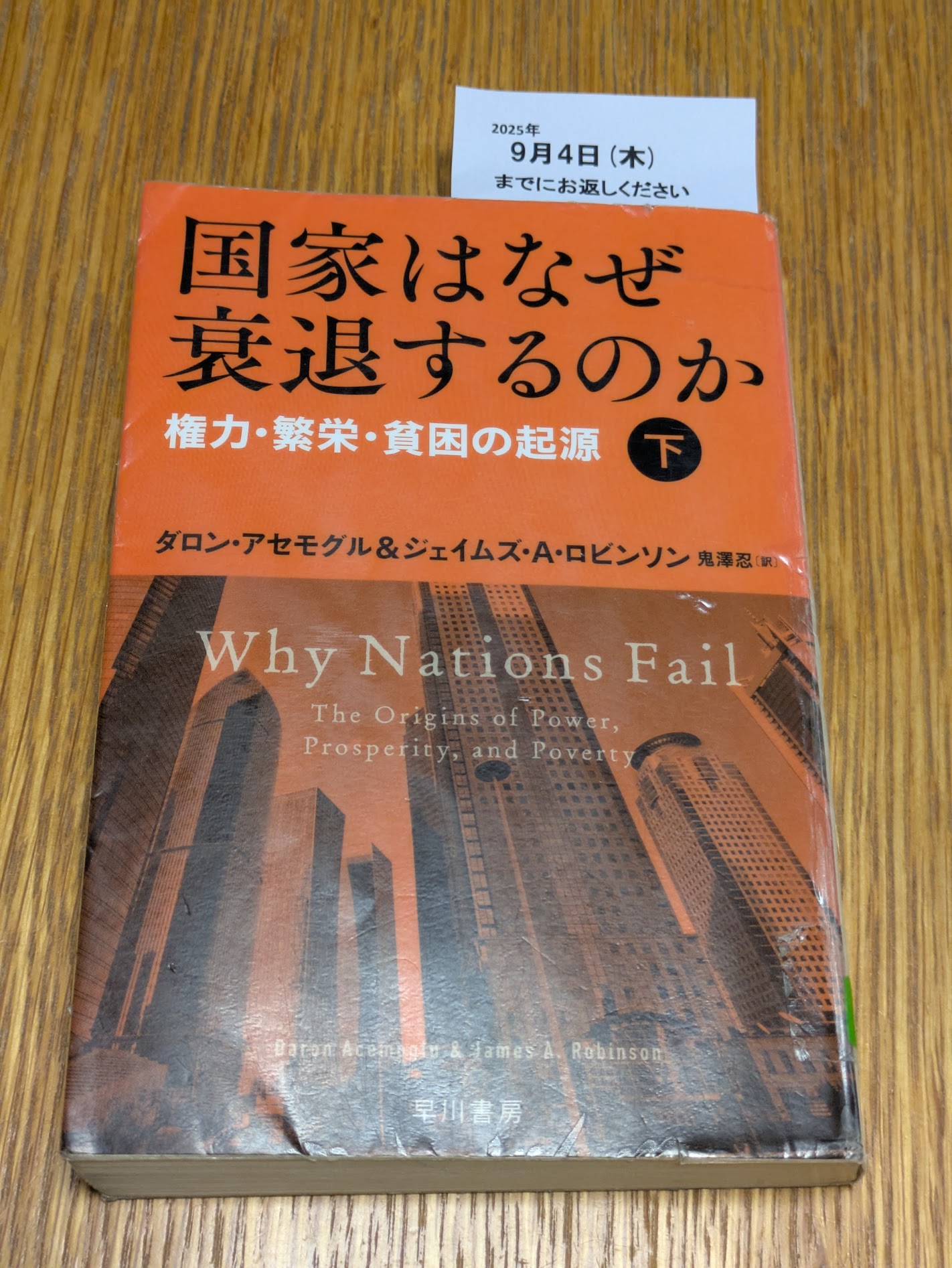国家はなぜ衰退するのか 下 ―権力・繁栄・貧困の起源―読了、思ったより早く手元に届いたのだが、やや多忙で読書時間を確保するのが難しかった。上巻に比べると引き込まれ度は低かったが、最後の方の
第13章 こんにち国家はなぜ衰退するのか
第14章 旧弊を打破する
第15章 繁栄と貧困を理解する
にはかなり考えさせられるものがあった。また、「第10章 繁栄の広がり」では日本の事例も出ていて、大久保利通の話が出てくる。その記述レベルを見ると、他の国の事例も恐らく幅はあっても同等レベルなのだろうと思わされた。
「第13章 こんにち国家はなぜ衰退するのか」で、中国や北朝鮮の将来を理由をあげて悲観的に解説しているのには納得感があるが残念に思う。本来、民にはその責任がないからだ。
「第14章 旧弊を打破する」で、中国がなぜ成長期に入れたかといった話題もあった。一番印象に残ったのは、ボツワナの話で、良質な権力掌握国家の利点がわかる。初めて知る話だったこともあるが、アフリカだから駄目ということではないのが実証されているのには大変力づけられた。しかし、最後の記述は「歴史はつねに成り行き任せの展開をするからだ。」である。つまり、繁栄を計画することは難しいし、包括的(Inclusive)な経済制度、政治制度の実現と維持は容易ではないことになる。安倍以降の日本を反省せねばならない。トランプのアメリカは、それ以上に将来に禍根を残すのが必定であることがわかる。安倍の暴走は、好ましくない事件で終わって、ようやく最近になって振り返りができるようになってきているが、その残滓は参政党や国民民主の台頭につながっていると考えるのが適切だろう。一度、道を踏み外してしまうと、一時の繁栄が得られたとしても持続性を取り戻すのは容易ではない。今一度、本書の視点でバブル崩壊を分析し直すとよいのではないかと感じた。
本文最終章の「第15章 繁栄と貧困を理解する」はわかりやすいまとめになっている。本文を読まないと理解できるとは思わないが、この章で理解が深まるのは間違いないだろう。やはり、最後は「偶然に大きく左右される歴史の成り行き次第なのである。」で締めくくられている。
巻末の解説では本書だけでない背景にも触れており、参考になった。
上巻ほどのインパクトはなかったが、やはり読んで良かった。
「偶然に大きく左右される歴史の成り行き次第なのである。」が現実なのはよくわかったが、それを超える理論が構築されることを期待したい。