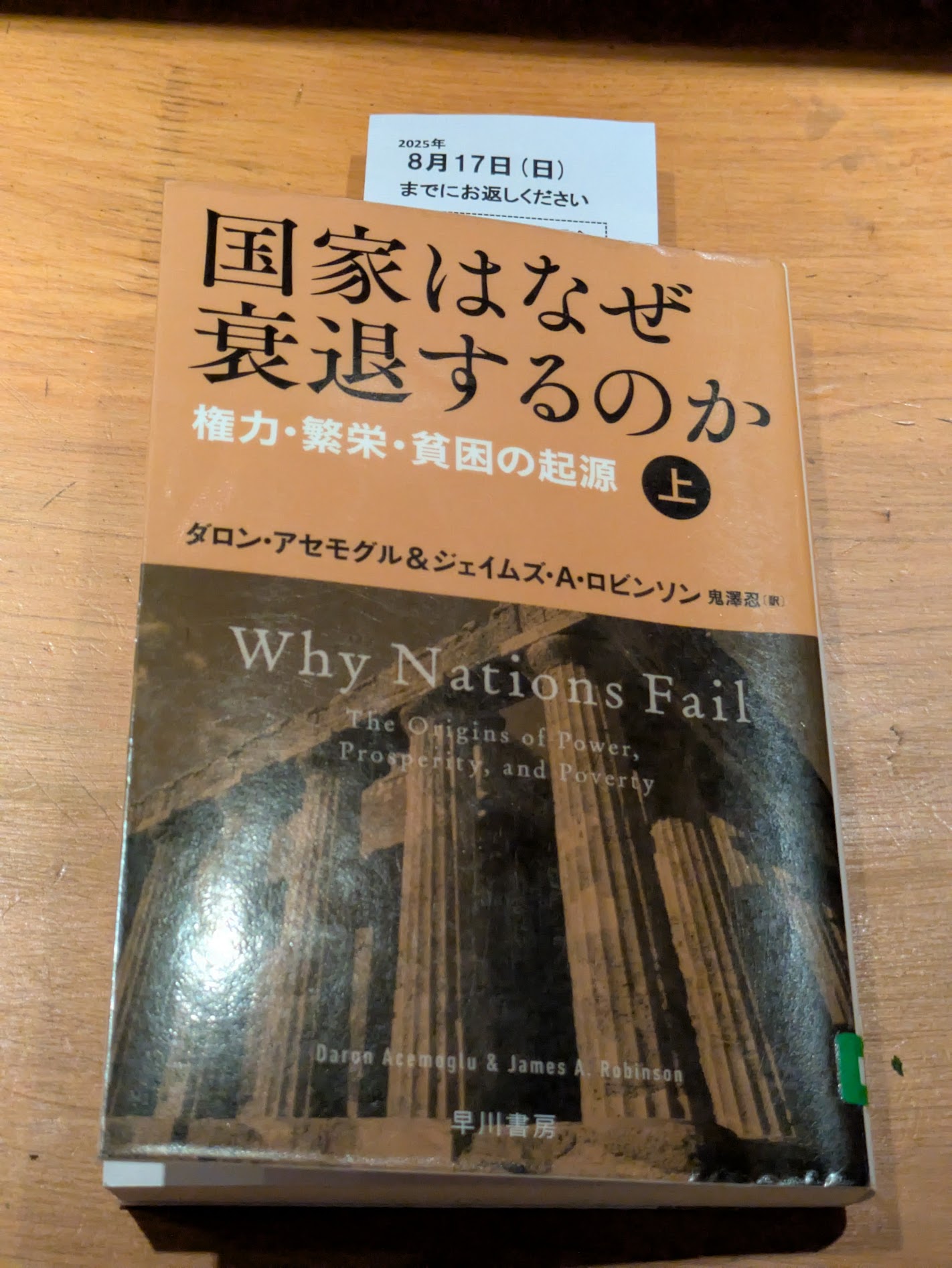国家はなぜ衰退するのか 上 ―権力・繁栄・貧困の起源― 上巻だけだが読了。極めて刺激的な本だ。下巻を楽しみにしているが、まだ予約待ちが長い。
包括的(Inclusive)な経済制度、政治制度(対比されるのは収奪的(extractive)な制度)が繁栄の決定的要素であるという主張を展開している。高い説得力がある。ただし、一度包括的な制度を確立しても、維持できないケースがあることも説明されていて、直線的な進化の道とは言えないことが分かる。
「第1章 こんなに近いのに、こんなに違う」、「第2章 役に立たない理論」で過去の仮説(地理説、文化説、無知説)を論破し、より大事なのは機能させている制度だということを明らかにしている。地理説で代表的なのは『銃・病原菌・鉄』のジャレド・ダイアモンドの理論だが、それだけで説明できない事例を第1章であげている。考えてみれば、戦国時代の領主の交代で、制度が変わってうまく行ったり行かなくなったりしているのだから、地理的な要因より制度が効くのはよく分かる。楽市楽座などは制度例と言えるだろう。
専制君主を倒しても、収奪的な制度が残れば、繁栄に向かわないという指摘はインパクトがある。ウクライナは、ソ連から独立できたが、収奪的な制度、腐敗は引き継がれてしまった部分があり、努力はなされているが、EUに入る障害となっている。悪者を倒せば幸せがやってくるというのが誤解であったことは、歴史の事実が証明している。EUの国の中にも包括的とは言えない国家もある。また包括性の維持に課題を抱えている国もある。
「第3章 繁栄と貧困の形成過程」で、安全な私有財産、公平な法体系、公共サービスの提供が包括的制度の要件としている。やりたい事業を自由に始められ、その事業を強奪されたりしないような環境が作れれば、自然と挑戦者が現れ、経済は発展するという仮説は適切に思われる。本書の本質的な主張はこの第3章にまとめられていると考えて良いだろう。
「第5章 「私は未来を見た。うまくいっている未来を」―収奪的制度のもとでの成長」で、ソ連の失敗を分析している。恐らく中国もこなままなら同じ道を歩むだろう。いくら出だしで成功しても、安全な私有財産、公平な法体系、公共サービスの提供が無いと、持続性はない。ただ、公平な法体系の中には、適切な規制も含まれるから、個々の民から考えて公平に見えないこともあるし、どの時間軸、どの空間軸で見るかによっても見え方は変わる。少子化が多くの地域で進んでいるのは、長期時間軸で公平な法体系が確立できていないと見ることもできるのではないかと感じた。グローバリゼーションへの抵抗感の高まりは、公平な法体系の実現困難性を示しているとも言えるだろう。
「第8章 領域外―発展の障壁」では守旧派の台頭について整理されているが、時代適応に遅れを取れば、空間軸をグローバルに取れば、競争に負けて繁栄が失われることが分かる。イノベーションのジレンマを想起させる。法治国家で法体系の中に、既得権益を守る作用が組み込まれれば、挑戦者が活躍できる余地を奪い包括性が損なわれてしまうということだ。品質の向上、維持に注目すれば成功した事業に様々な規制をかけるのは公共の福祉に資する。ただ、生き残ったものにとっては参入障壁という武器となり、当初のイノベーターが守旧派に落ちるリスクを含んでいるということだ。包括性の維持は容易ではないことが分かる。官僚や政治家に十分な理解がなければ国家も道を誤るということだろう。
下巻の目次を見ていると、どう包括的な制度を維持、発展させていくかについて論じられているに見える。楽しみにしたい。