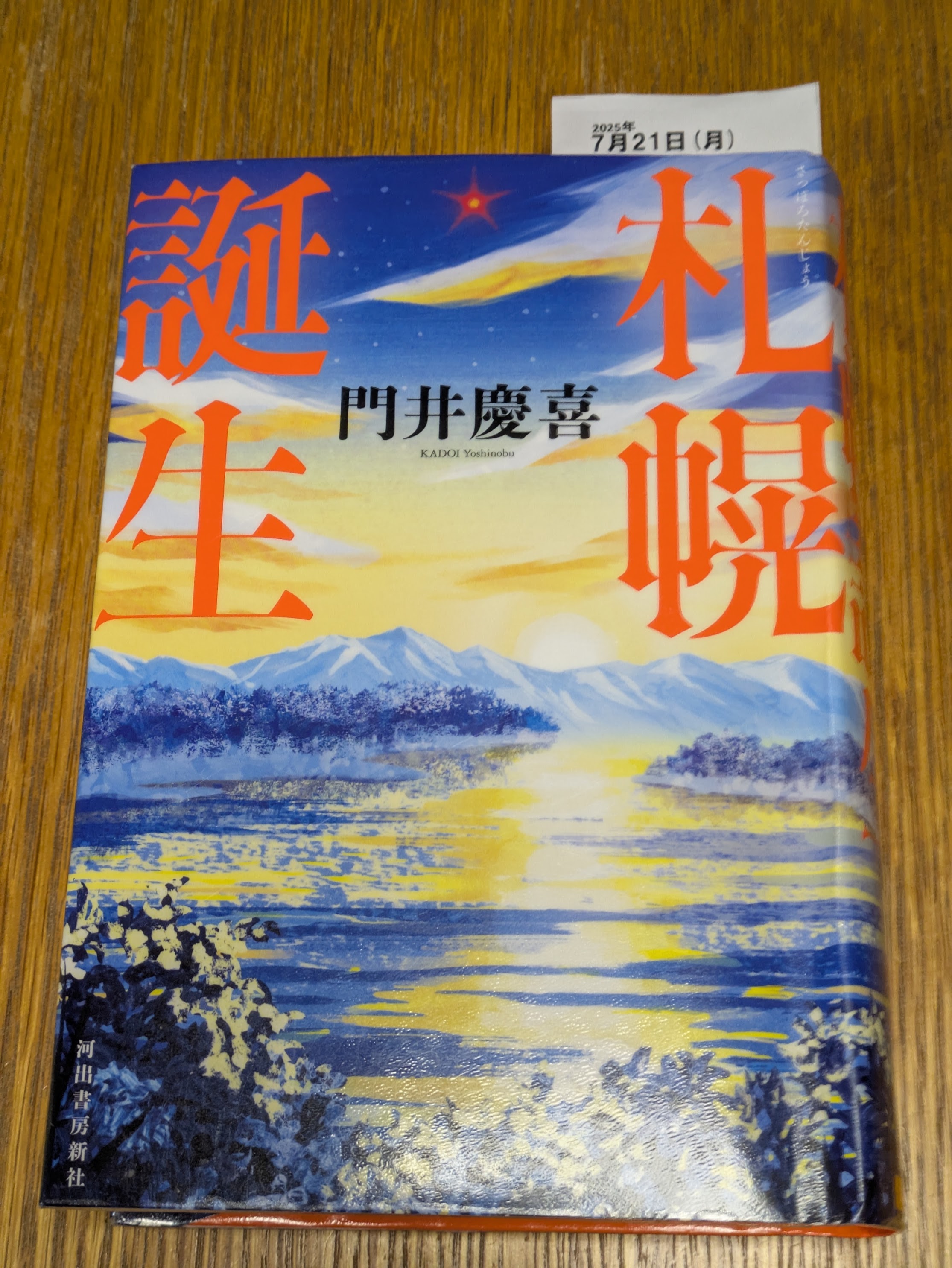札幌誕生読了。島義勇、内村鑑三、バチラー八重子、有島武郎、岡崎文吉の5人のことが書かれていて、史実に基づくだろうが、それぞれの感情や発言が書かれている部分は著者の想像で、恐らく現実との差異は小さくないだろう。小説だからそれで良いのだろうが、内村鑑三や有島武郎は著作を読んだこともあり、様々な形で情報に触れる機会が会ったので、結構違和感があった。一方、島義勇、岡崎文吉の話は、都市計画に関わるもので興味深く読んだ。
札幌は整備された街という印象が強い。一章に出てくる大友堀(創成川)は豊平川の分岐地点近傍となる幌平橋には行ったことがあるし、豊平川横を数kmに渡って散歩したこともあるが、石狩川との関係も札幌開拓のためにその水路が役に立ったことも知らなかった。
現在の札幌市は人口約200万の大都市で、新千歳空港はいつも混み合っていて多くの利用者がいる。かつては、ほとんど人のいない場所だったのは事実だろう。明治政府は手を付けなければロシアに取られてしまうと考えていたという話は考えてみれば理解できるが、それで金がついて開発が進んだというという話につながると、当時の政治家や官僚が結構グローバルな視点を持っていたことに気付かされる。
内村鑑三、有島武郎は札幌農学校出身で、ピューリタニズムの流れをくむ。バチラー八重子はイギリス人学者の養子になったアイヌの人。英米にも日本への文化投資がなされていることにも改めて気付かされる。北海道が異文化の接点となっていたのも興味深い。開拓の時期、特に成長期は貢献可能な人の力は属性にかかわらず借りざるを得ないから、接点は熱くなる。本国からの金も役に立つ。
恐らくそれは現代でも変わらないが、残念ながらトランプは文化投資を止め、日本も内向きになっている。本当は現代のフロンティアが機能する土地に関わって、新たなイノベーションが生まれるのが望ましいのだが、期待し難いのが残念。
札幌誕生はかつての話を書いた小説として魅力的だが、本当は現代の札幌誕生のようなことが世界の少なくない場所で起きているべきなのだ。新たな繁栄が始まる場所に行って、関わりたいものだと思った。