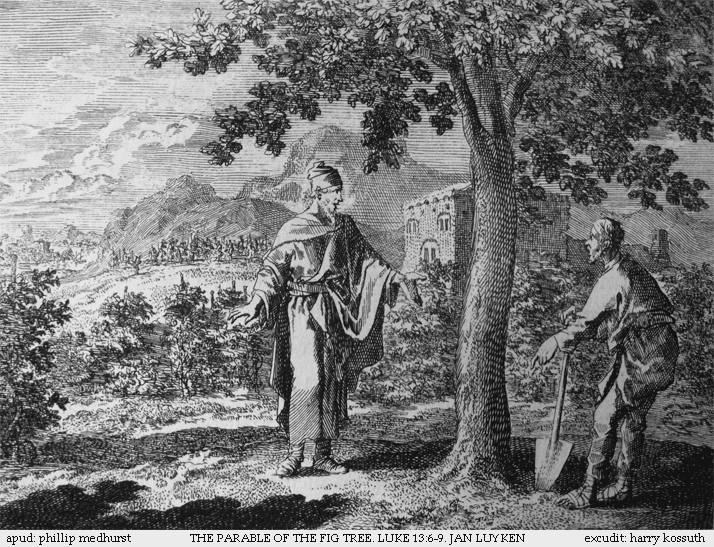今週も福音のヒントの箇所から学ぶ。今日の箇所は「四旬節第3主日 (2025/3/23 ルカ13章1‐9節)」。3年前の記事がある。2つの段落とも直接的な並行箇所は見当たらない。
福音朗読 ルカ13・1-9
1ちょうどそのとき、何人かの人が来て、ピラトがガリラヤ人の血を彼らのいけにえに混ぜたことをイエスに告げた。 2イエスはお答えになった。「そのガリラヤ人たちがそのような災難に遭ったのは、ほかのどのガリラヤ人よりも罪深い者だったからだと思うのか。 3決してそうではない。言っておくが、あなたがたも悔い改めなければ、皆同じように滅びる。 4また、シロアムの塔が倒れて死んだあの十八人は、エルサレムに住んでいたほかのどの人々よりも、罪深い者だったと思うのか。5決してそうではない。言っておくが、あなたがたも悔い改めなければ、皆同じように滅びる。」
6そして、イエスは次のたとえを話された。「ある人がぶどう園にいちじくの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。 7そこで、園丁に言った。『もう三年もの間、このいちじくの木に実を探しに来ているのに、見つけたためしがない。だから切り倒せ。なぜ、土地をふさがせておくのか。』 8園丁は答えた。『御主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って、肥やしをやってみます。 9そうすれば、来年は実がなるかもしれません。もしそれでもだめなら、切り倒してください。』」
3年前の記事では「「悔い改めなければ滅びる」という標題がついているこの箇所は、私には印象が薄くて、何を意味しているのかこれまであまり考えたことがなかった。」と書いている。シロアムの塔の事件は良くわかっていない。Strong's Greek: 4611. Σιλωάμ (Silóam)によれば、シロアムという単語は新約聖書で3回しかでていなくて、今日の箇所とヨハネ伝9章のシロアムの池で目を洗う話で2回でてくる。福音のヒント(1)、(2)を読み直しても、何かしっくりこない。
「実のならないいちじくの木」と見出しがついている6節からの部分については3年前は感想めいたことしか書いていなかった。biblehubではこの箇所の引用として、イザヤ書 5:1-7が挙げられている。その箇所の見出しは「ぶどう畑の歌」で丁寧に植えて育てたのに酸っぱいぶどうが実ってしまった話で、神がイスラエルの民が期待に反していることを嘆いていると読める箇所である。
福音のヒント(3)でも触れられているが、園丁が人間イエスで、主人である神に忍耐を求めていると読むことはできる。聖霊が共にある人間イエスあるいは預言者イエスには人に見えないことが見えていて、さらに、イエスの人間性に基づいて人間の哀れに気づくことができて、とりなしの思いを持っていたと考えることもできる。
人間として生きたイエスの人間としての愛はどのようなものだったのかを想像しても良いのではないかと思う。人間イエスは失敗もあったし、無力感は相当感じていたはずだ。でも、道は示されていた。自分がその道を歩むことを決断していたとしても、道が示された人間の多く、あるいは全てが、道に従って生きることが困難であることを実感していたのかも知れない。
来年は実がなるかもしれませんというとりなしが2000年経ても未だに有効だということなのだろう。良い実を結ぼうとする努力はやめてはいけない。
※画像はWikipedia経由のAn etching by Jan Luyken illustrating Luke 13:6-9 in the Bowyer Bible, Bolton, England.