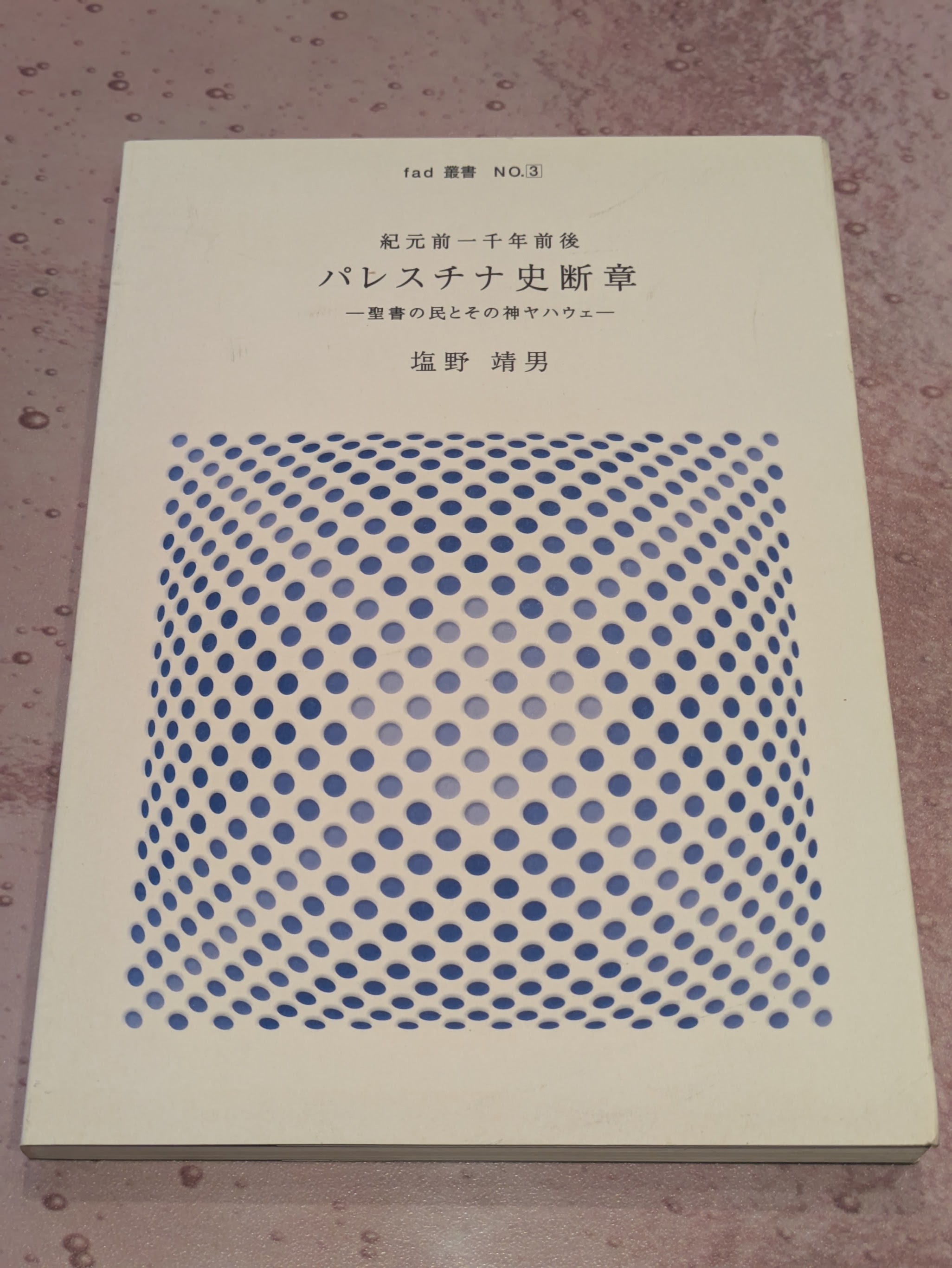積ん読書から選んで『パレスチナ史断章』を読んだ。学者の一つの解釈と言って良いと思うが、筋が通っていてインパクトは大きい。
前半の『特殊イスラエル史からパレスチナ史を求めて』は、パレスチナ定着時のイスラエル、ダビデ王、ソロモン王についての言及があり、その後の5章を割いて記述している。後半は関連する説教の記録である。著者の塩野氏は東神大の卒業生だが正教師にはならずに農民兼伝道師として生きた人で学生運動の影響を強く受けている。
前半の部分を思い切って捨象すれば、奴隷だったユダヤ人集団がエジプトから出エジプトしてカナンの地、パレスチナの地に入植(侵攻)し、既に成熟した文化、経済制度を確立していた都市国家と衝突しながら何とか生き残ってきた話を、現実はどうだったのかについて仮説検証している。サウロという愛国者は一定の軍事的成果は出したが、所詮カナンの(バアル神を仰ぐ)都市国家群から見れば一過性の権力者だった。はぐれもので暴力的だったダビデがカナン的文化との融和策でサウロ時代に確立された王という地位を奪取したと説く。ソロモンが築いた神殿は恐らくカナン的なもので、一部はユダヤ的であったが、ソロモン自身はどう振る舞えれば生き残れるかを考える独裁者で民から搾り取れる限り収奪し、ユダヤの愛国者をできる限り懐柔したと言う。ソロモンの力が弱ったときには、南北に分離した王国が現れ、それぞれ現実的な融和派と排他的愛国者の対立関係の中、結果的に凋落した流れがわかりやすく書かれている。
多分、その分析は当たっているだろう。聖書以外の文献で、ダビデやソロモンが有力だった証拠はほとんどなく、時代も聖書で記述されている時期とはずれている。聖書の記述は、申命記史家の捏造が多く含まれているのは明らかで、モーセの実在も怪しいし、王政の根拠を作ったサムエルも極せまい範囲の宗教指導者に過ぎなかったのは事実だろう。
塩野氏の事実は事実としてできるだけ客観的に見ようとする姿勢と、しかしそれでも信仰は失っていないように見えるところに凄さを感じる。
ちょうど、今の時期に、積ん読から手に取ったのは、その時だということかも知れない。ベテラン信徒にはぜひ目を通していただきたい書籍である。