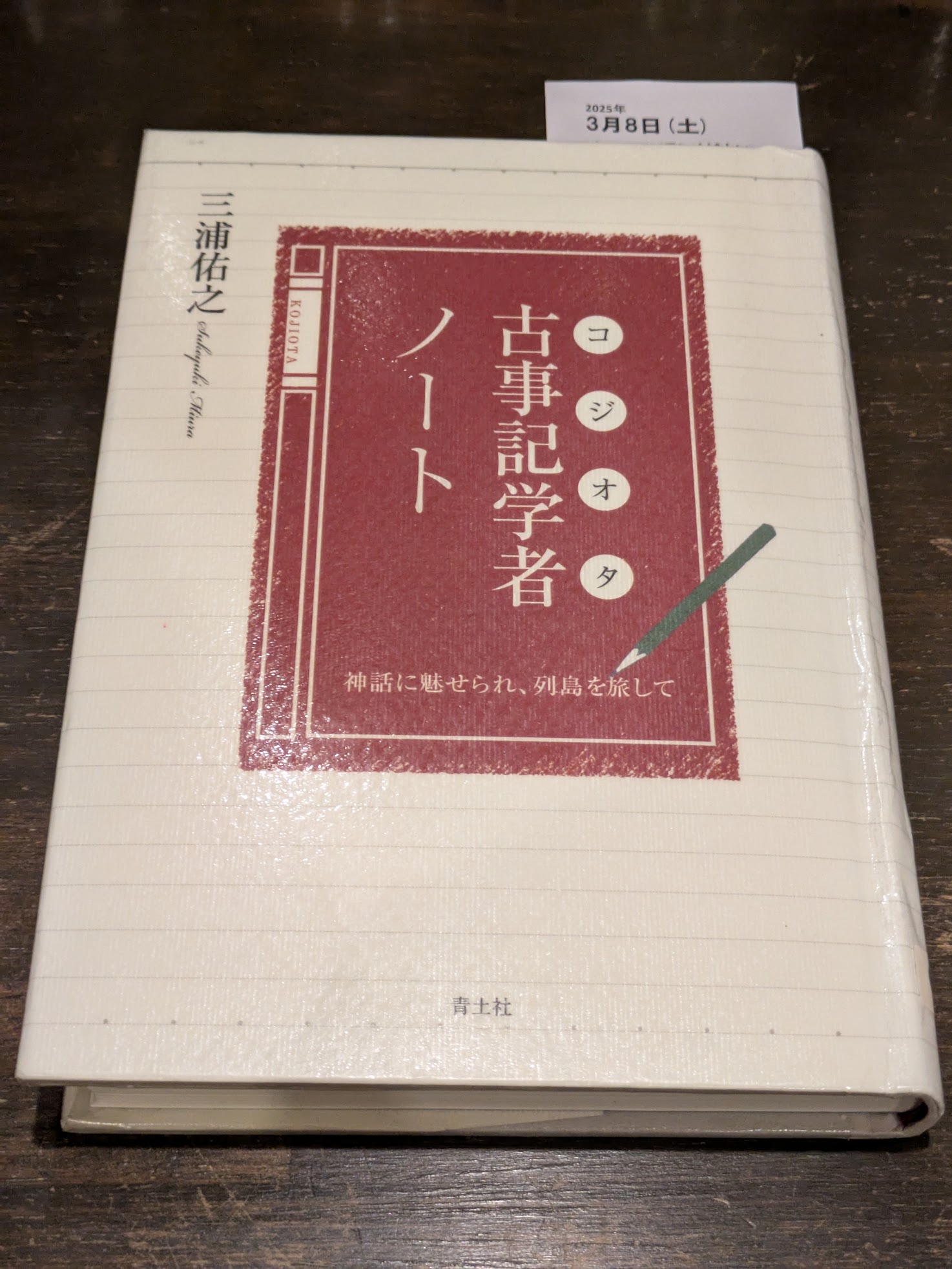私が通った幼稚園は神社付属だった。柏手を打つことは当たり前のこととして受け取ったし、疑いも持たなかった。母が教会に通うようになり全く新しい宗教に触れ、教会学校に通うようになって多様な価値観の存在を知り、その価値を理解できるようになった。それでも初めて海外に出た1987年から20年を経ても日本は特別な国という呪縛からは逃れられなかった。今なら、冷静に記紀が読めるような気がする。
『古事記学者ノート(コジオタノート)』読了。しばらく前に『大学生・社会人のためのイスラーム講座』を読んだ時に古事記の話が出てきたので、ちょっと見てみようと思って借りたのだが、想像を超えて面白かった。
出だしは手塚治虫『火の鳥』へのコメントで、「歴史とは何か。古事記や日本書紀などを研究対象とするわたしは、いやでも歴史書に記述された「真実」について考えさせられる。」と書かれている。古事記のヤマトタケルと日本書紀の日本武尊は記述が大幅に違うことから、史実がそのまま記されているわけではなく、筆者あるいはパトロンの思惑が入っていることに触れ、手塚治虫の解釈の面白さについても触れている。著者の三浦佑之氏は懐疑的、批判的アプローチを取る学者で2012年が古事記編纂1300年にあたりブーム化していることにも触れている。ただし、彼は古事記の成立の時期について異なる意見をもっている。
私が、イスラーム講座を読んで感じたのは、イスラム教ではイエスは預言者と位置づけられているが、その系譜はイシマエルの末裔として書かれていて、イサクの後継ではないなど、正史を編纂しようとすれば、かならず権力者の都合で改ざんされてしまうという現実だ。古事記と日本書紀の食い違いを分析し、同様のアプローチをユダヤ教、キリスト教、イスラム教の伝承比較に応用することもできるだろう。新約聖書の福音書にあるイエスの系図もマタイ伝、ルカ伝で異なっているし、どう考えても怪しい。意図的に編集されたと考えざるを得ない。古事記は出雲の正史、日本書紀は奈良の正史と考えることもできる。奈良は記紀の発祥をうたい、出雲大社は天皇を受け入れない。権力闘争の勝者は奈良側で、それを明治政府が利用して後に紀元2600年とか事実無根の正史を教科書に収載し悲惨な侵略戦争を正当化したことを本書で改めて教えられた。
魏志倭人伝、捕鯨の話も出てきて、古の文書には昔の生活や技術の記録も残されていて純粋に進歩の歴史を追うことができることも学んだ。実際にその地に足を運び、古文書の知識を踏まえて肉眼でその地に残されているものを見れば他の人とは異なる景色を見ることができることも興味深かった。
遠野物語の話も興味深く、いずれは読んでみたいと思わされた。
構成としては、第一幕「吹きかえす 神話再生」、第二幕「あおられる 旅の足跡」、第三幕「うそぶく 時評風に」からなっている。第三幕は「疑うことから始めたい」、「皇紀二千六百年、その他」など、反体制的なメッセージが力強い。ちょっと尻すぼみの感じもあったが、金印の話など歴史修正主義は金や権力に結びつくし、娯楽として消費するだけではなく例えば安倍・高市的な国粋主義の強制の原点となる。まず事実を確認することから論理を組み立てるべきという三浦氏の姿勢を尊敬する。
次は、三浦氏の口語訳古事記を読んでみようと思う。