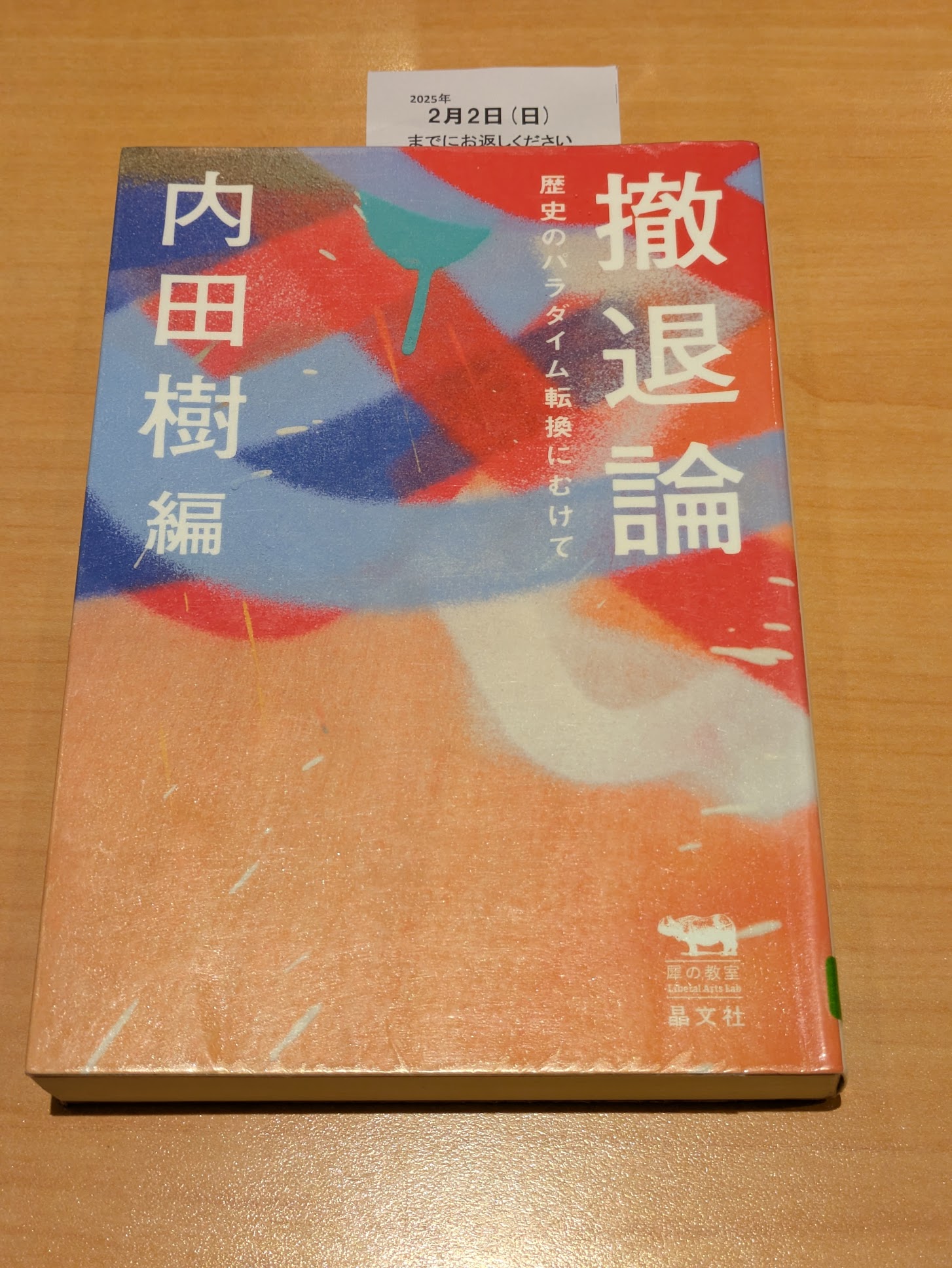撤退論を読み終わった。思いの外刺激的な本だった。
もともとは佐谷さんの内田樹(編・著)『撤退論〜歴史のパラダイム転換にむけて』の記事を読んで、今後読みたい本に登録しておいて、予約してからなかなか順番が回ってこなかった本である。いくつも印象に残った記事はあったが、三砂ちづる氏のWithdrawalは特に印象に残った。次は、タルマリー渡邉夫婦の2件の記事である。その3件とて僅差で、最初から最後までどれも夢中になって読んだ。
比較的近い年齢の筆者が多かったこともあるが、意見は異なることはあっても感覚は理解しやすかった。逆に言えば、20年以上年下の人には共感が得られないかもしれない。
自分なりに撤退について考えた内容を尺無視で書いておこうと思う。
撤退という言葉は、今まで進んできた道を引き返すという意味だろうが、ただ引き返すというのでは芸が無い。まず、このまま進んで行けばどうなるのかを考えて次の道を探すということだろう。大きくは、人類がという話となり、国や地域あるいはコミュニティ、小さくは個人の問題と捉えることができる。幸福追求論とも言えよう。
日本という国で見れば、強い国を目指して破綻したことを思い出せば良い。強制的に撤退させられ、独立も失われた。幸いなことに、当時の占領国の米国が大きな流れとしては自由と民主主義を理想として掲げていたこともあって、その思想を受け入れることができれば再独立を許すという状況が与えられた。民衆はもう戦争は懲り懲りだと思っていたし、そもそもなんとかして食っていかなければいけなかったので、必死に生活再建に邁進した。為政者もなんとか民衆が生き残れる道を探った。考えてみれば、米国から送られた人たちが、民衆がどれだけ死のうとも絞り尽くせるだけ絞りつくそうという動きがなかったのは本当に幸運だったと言える。もちろん、きれいなことだけではなかったし、日本の為政者の中にも強い日本、権力奪取を指向した人々もいた。様々な負の遺産も正の遺産も残っている。最近暗殺された強い日本を指向した安倍晋三も、第一次トランプ政権で、日本が不当に評価されないように尽力したことは評価されなければならないし、TPPで単なるアメリカの属国でない未来を指向したことも評価されて良いだろう。私は、彼が指向した美しい日本という道は懐古的で再び戦争と破綻に至る道だったと考えているが、彼の死によって、そのスピードは弱まった。無理やり進めるために用いられた統一教会からの援助や、不正に集められた金が少しだけ明るみに出ただけで与党は過半数を失い、無理を通すことはできなくなった。同じ道をそのまま進むことはできなくなったのである。
宗教だろうが、デマだろうが、Fake Newsだろうが、汚れた金だろうが、使えるものは何でも使うという権力には大きな副作用が伴う。事実を尊重するより、勝てば官軍的な、強いものに迎合する価値観が支配的になり、今はそれが自民党に対しても牙を剥くようになっている。自業自得でもあるが、つきつめればそれは主権者の責任である。
その日本では、激烈な人口減少が進んでいて、24年の新生児は70万人を切ったと言われている。高齢化が進み、従来の経済モデルの持続性がないのは明らかである。なぜそうなったのかについては多くの仮説が提示されているが、正直に言って私は原因が良くわからない。私には子供がいないので、少子高齢化の原因の一人だが、だからといってどうにもなるものではない。運もあるし、国が強制したり、それを罰するようでは自由を失うことになる。
世界規模で見れば、地球温暖化はどう考えても現実の脅威である。それを見ない道を提唱する人も逃れ得ないのだが、老人は自分の残りの時間が少ないから、私には関係ない(逃げ切れる)という甘いささやきが迫ってくる。自己中心になれば(あるいは都民ファーストとかアメリカ・ファーストといった扇動になびけば)、今の享楽を優先してしまう。次世代への責任を負おうと思えるためには精神的に支柱か経済的安心感が必要となる。だから、格差は社会を破壊するのだ。新自由主義は資本主義よりさらに格差肯定だから、社会破壊を加速する。Alternative Factを許せば、さらに現実を見る、重大な課題に立ち向かうより、自己満足を追求することになるだろう。
南北問題やガザの悲惨を引くまでもなく、格差はとても大きい。米欧はもちろん、日本にも、生活向上を求めて移動してくる人は少なくない。現実的に経済的に許容できる範囲は限られるから、全てを受け入れることはできない。そうなれば、選別あるいは裁き(命の選別)は避けられない。それは現実である。私は乗り越えるべき課題だと考えるが、現実は夢想を短期的には許さない。豊かな国、弱くない(むしられない)国を目指すのは自然なことだと思う。一方で、一人の人として外国人や様々な事情を抱える人に接すれば、その人が誰とも変わらない一人の人間であることに気が付かされる。人種や国籍、性別や来歴は、些末な属性に過ぎないことが分かる。強さを扇動する人間は、それに気が付かれては困るのである。
成長基調にある時は、需要も拡大基調になるので、頑張ればなんとかなるという気持ちになれるが、頭打ち、縮小期には今まで稼げてきたことで継続的に稼ぎ続けることは難しく、マクロで見れば未来は暗い。もちろん、そういう時期にも成長する産業はあり、未来に期待が持てている人はいなくはならない。しかし、全体として経済が縮小していく中で、成長の果実を得る人がいるということは、その分、割を食う人がいるということだ。言い換えれば、多くの既得権益は失われる運命にあると言える。年寄りの視点で言えば、年金で食えると考えるのは現実的でないというとても不都合な未来が到来する。
あまり楽しくはないが、衰退期は小さな無駄の削減、あるいは低価格かつ高品質を追求する活動に力を入れなければいけないだろう。実は、デフレ時代はそういう時代だったのではないかと思う。物価は上がらないし、所得も上がらないが、都市部では生活水準が特に低下する実感はなかった。一方で、消滅の危機に瀕する地方は確かに存在する。インフラのメンテナンスができずに生活水準が維持できないケースもある。自給自足型にライフスタイルを変えて生き残るという道もあるだろうが、誰にでもできることではない。
インフラ維持コストをどう小さくしていくか、どう外界との経済的交流を強めていくかを考える必要があるだろう。
高齢者には抵抗があるかもしれないが、デジタル化と機械応用は避けては通れない。コンパクトシティ化も避けて通れないだろう。同時に、人の住まない場所をどう維持していくのかも重要な観点となると思う。都市部でも橋や道路、水道施設などのインフラが耐用年数を迎えて事故が起き始めている。
特に、デジタル公共財の充実が重要だと思っている。
従来の公共財は、公園などの固定資産的側面の強いものだったが、今は国連がDPGAで推奨しているデジタル公共財(Digital Public Goods)のような物理的な場所に依存しない公共財もある。これを充実させることが社会福祉を増進させ、格差の縮小に役立つだろう。誰かが、先行して挑戦しなければならないし、すでに挑戦した先人は少なくない。消えていったものもあれば、資本主義時代にも関わらず、生き残っているものもある。応用から考えると、まず自分たちの実態を適切に把握できるようになることが重要だろう。日本では統計局がパブリックデータを収集してきた。OECDでも様々なデータが収集、解析されている。COVID-19の時期にはWHOのデータはとても参考になったし、下水道でウィルス量を測定するとか、国によって異なるデータ収集方法があることなどデータの公開は多くの知見を与えてくれた。データだけでなく、それを多少の誤差は許容しても複数ソースのデータを統合分析してデファクト標準指標として把握可能にするようなソフトウェアの存在も大きい。今いるところや、訪問先の大気汚染や水質、感染リスクを可視化することも社会福祉的には有効だが、一方で情報の独占は権力掌握の基盤となるから大企業や政府は既得権益を守るために情報公開に消極的な傾向がある。しかし、サイロ化には持続性がない。
GPSのような政府あるいは軍が主導したものもあるが、Google等、民間が主導してGoogle Mapsのように公共財に近い存在になったものもある。GTFSのようなデファクト標準は生活を変える。もちろん、多くは栄枯盛衰で消えていくが、残るものは残って進化していく。
公共財は、原価ゼロではない。メンテナンス費用もかかる。行政が担うものには税金が投入されている。Google Mapsは、そのデータを活かした商売をすることで、個々人の受益者負担をゼロにしているが、原価は相当大きい。DPGはただではない。それが画期的なものであれば、発明者にも相当な報いが必要だろう。
国際的に税で解決する方向性もあるかもしれないが、新たなビジネスモデルが必要となるのは間違いない。
国連に限らず、EUもオープンソースに積極的だが、まだ持続性のあるビジネスモデルが確立されているとは言えない。クラウドファンディングなどの手法を用いても良いので、民間からの挑戦が必要な分野だろう。国際NPOあるいはCommunity Coworkingが重要な役割を果たすことになるだろうと予想している。