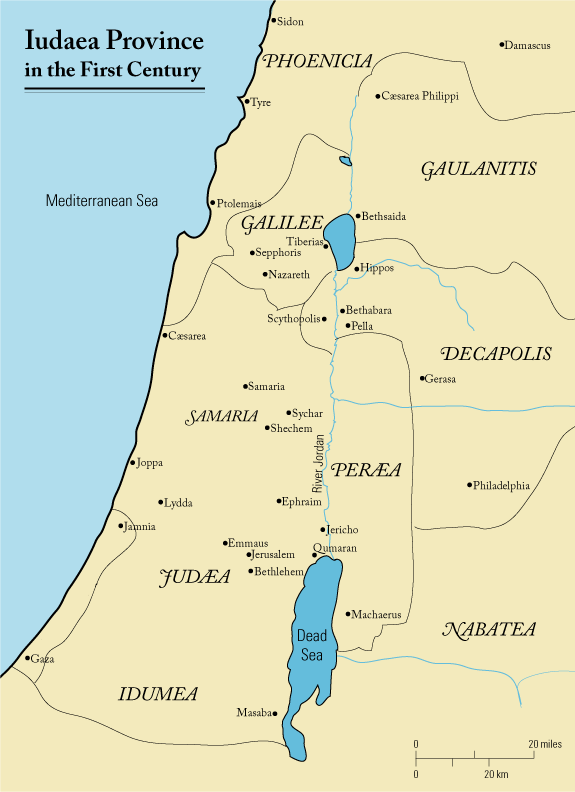今週も福音のヒントの箇所から学ぶ。今日の箇所は「年間第28主日 (2025/10/12 ルカ17章11-19節)」。並行箇所はない。3年前の記事がある。
福音朗読 ルカ17・11-19
11イエスはエルサレムへ上る途中、サマリアとガリラヤの間を通られた。12ある村に入ると、重い皮膚病を患っている十人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったまま、13声を張り上げて、「イエスさま、先生、どうか、わたしたちを憐れんでください」と言った。14イエスは重い皮膚病を患っている人たちを見て、「祭司たちのところに行って、体を見せなさい」と言われた。彼らは、そこへ行く途中で清くされた。15その中の一人は、自分がいやされたのを知って、大声で神を賛美しながら戻って来た。16そして、イエスの足もとにひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。17そこで、イエスは言われた。「清くされたのは十人ではなかったか。ほかの九人はどこにいるのか。18この外国人のほかに、神を賛美するために戻って来た者はいないのか。」19それから、イエスはその人に言われた。「立ち上がって、行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。」
福音のヒント(1)でガリラヤ、ユダヤ人、サマリアの話が出てくる。サマリアは北イスラエル王国の都で、ソロモン後、紀元前10世紀に分離。北イスラエルは200年間存続したが王朝ははるか昔に滅亡している。ガリラヤはユダヤ人入植地で大きな飛び地的な存在だったらしい。18節で「この外国人(ἀλλογενής (allogenés)、この箇所のみで用いられている単語)」と書かれているが、もともとは同胞で、版に違いはあるがモーセ五書を聖典としている。デカポリスはギリシャ人の入植地で言語的にも民族的にも異なる。
サマリアという単語(Σαμάρεια (Samareia))は新約聖書で11回出てくるもので、ルカ伝では17:11のみ、他は、ヨハネ伝と使徒行伝で出てくる。サマリア人(Σαμαρείτης (Samarités))は9回。マタイ伝では10:5のみで弟子の派遣時にサマリア人の町に入ってはらなないと命じる際に用いられている。マルコ伝ではどちらの単語も出てこない。
ルカ伝9章の「サマリア人から歓迎されない」に記録しているが、エルサレムに向かう道としてサマリヤを通過するのは困難だったようで、デカポリスに入ってヨルダン川沿いを南下したのかも知れない。
Ellicott Commentaryでは、ルカ伝の著者がユダヤ人以外に福音が開かれていることを示しているという意味のことが書いてある。マタイ伝がユダヤ人ファーストで整理されているのに対し、ルカ伝は異邦人伝道に焦点を当てているのが分かってくる。
イエスが生きていたガリラヤはデカポリスと隣接し、その地への地中海からのアクセスの経路となっていたようなので、エルサレムより遥かに多様性に富んでいたと思われる。ギリシャは地中海の民で、陸路ではローマ(バルカン半島経由)ともデカポリス(イスタンブール経由)とも遠く離れているが、地中海(沿岸航路)を使えば、遥かにアクセスは容易になる。パウロはタルスス(現トルコ、キプロス北方、キリキア属州)出身で活動範囲は広く、ルカ伝の著者はパウロとの接点が多かったようなので、視点はマルコ伝、マタイ伝と比較して相当国際指向と言える。
さて、本日の福音朗読箇所の話であるが、この通りの事実があったのかはわからない。ガリラヤからエリコを経由してエルサレムに陸路で行ったことは間違いないと考えられるので、サマリアを通っていったか、デカポリスを経由したかのいずれかということになる。両方通ったかも知れない。その過程で、サマリア人の病人に対して治癒奇跡を行った可能性はあるだろう。律法は共通でサマリアの祭祀に治癒確認を得る必要があった。治癒が確認された後、戻ってきた人は一人だったという話となる。常識的に考えれば、他の9人はサマリアの日常に戻っただけで、感謝の心がなかったとは言えない。むしろ、戻ってきた一人は、サマリア分派からイエス派(当時はユダヤ教内の新興勢力)に改宗したと言えるわけで、この地においてはかなり異常事態が発生したと考えてよいだろう。ルカ伝の視点では特に記録しておきたい話となる。並行箇所のないスクープ的な記事と言ってもよいだろう。
国が別れて約1000年が経過し、分裂した国家間で何度も戦争が起きた歴史がある。双方に我らこそが正当な神の民という主張を続けているので、ユダ王国が滅亡してから500年が経過しても再融合には至らなかった。これは、不思議なことだと思う。イエスはアケメネス朝の公用語だったアラム語を用いていたと言われている。サマリアでもエルサレムでもアラム語は通用していたと思われる。また全てローマのユダヤ属州に含まれ、その公用語はギリシャ語である。パウロはギリシャ語を話すユダヤ人でかつローマ市民だった。ローマでの国教化を意識していただろうから、脱ユダヤは解決しなければならない課題で、ルカ伝の著者、編集者は強く影響を受けて福音書を編纂したと思われる。
一方、現イスラエルは、ユダヤ人国家法(2018年)でアラビア語(アラム語から派生)を公用語から除外し、ヘブライ語のみを公用語としている。剣呑でサンヘドリン的な旧約の民に回帰しているようで、懲りない人々に感じられる。持続性は感じられないが、一人ひとりを見れば考え方は多様。ナショナリズム政治は内外の多くの人を殺してしまうのが歴史の教訓だろう。結局、保守は国を滅ぼす。
※画像はJudaea province in the 1st Century CE。ガリラヤは明確に境界があるが、サマリヤ・ユダヤ間には境界線が見当たらない。