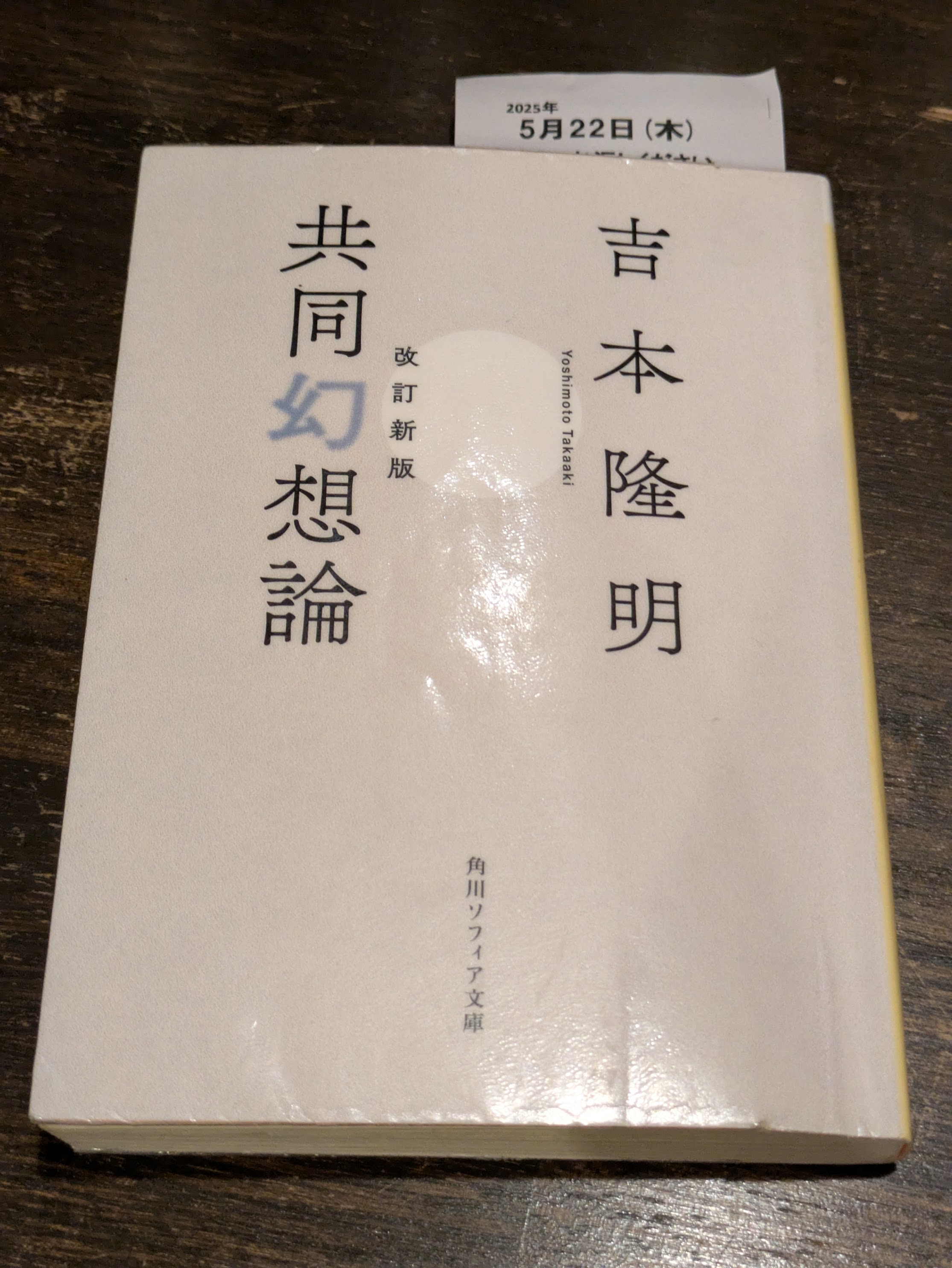共同幻想論読了。遠野物語経由で到達した本。古事記の引用もある。前半は、遠野物語や古事記の共同幻想のコンテキストで解釈していて、後半は描き下ろし。最終2章の規範論、起源論で国家の成り立ちについて考察している。宗教→法→国家の流れで整理されていて、魏志倭人伝の記述から、国家は他の国家との通商や争いの中で確立されていくのがわかる。
角川文庫版の序で、「国家は幻想の共同体だというかんがえをわたしははじめにマルクスから知った」と書かれている。
以前『想像の共同体』を読んだ記憶がよみがえる部分もあった。ベネディクト・アンダーソンは、ナショナリズムは発掘されるものだと書いている。日本の右派であれば天皇の歴史の捏造で、それを旗印にして人々に選民思想と序列化を促す。
現代であれば、クルド人は国家を持てていないが、クルド人ナショナリズムは厳然として存在していて、独立による方針決定の自由を望んでいる。様々な共同体があり、独立運動はもっと小さな単位でもたくさんある。
カトリックは国家ではないが共同体で、ナショナリズムがある。映画コンクラーベではないが、組織は権力闘争から自由にはなれない。イエスは支配被支配の構造を否定したと考えているが、教会は実際にはその構造を有する。ただ、慎重に国家化しないことで、滅亡を免れてきた。
共同幻想、対幻想は共に難解な概念で、共感はできても理解は難しい。古事記からどう共同幻想が構築されているかを説き、遠野物語から素朴な現実を視て共同体の成立過程を説明している。
書籍としては、序が長くてテンションが下がった。巻末の解題も鼻について印象が悪かった。しかし、本文はとても興味深く、最後の解説も悪くない。読んで良かったと思っている。時代のせいもあるかとは思うが、日本に対する意識の大きさが残念に感じられた。